“塩切り鮒”の予約販売を行っています。
詳しくは、
“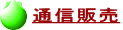 ”を
”を
ご覧ください。
“内臓部分は、卵を傷つけないように、えらのところから取り出します。”
“ホンモロコの素焼き”
“ホンモロコの南蛮酢づけ”
厳しい冬が過ぎ、小アユ漁やフナ漁が始まると、“沖島の春”到来です。
沖島の春は、島の所どころに桜が咲き、山では“蕨”、“筍”、“よもぎ”などの山菜も採れたり・・・と
のんびりとした懐かしい春の風景に出逢えます。
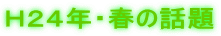
今年も沖島に暖かな春がやって来ました。今年は春の到来が遅く、桜の開花も例年に比べ遅めでした。また、春に最盛期を迎える小アユ漁も遅れています。
そんな中、今年は“ホンモロコ漁”が好調で、昨年に比べて漁獲量が増加しており、特に沖島周辺で増えています。
 “ホンモロコ漁”好調 “ホンモロコ漁”好調 |
今年の春は昨年に比べ“ホンモロコ漁”が好調で、特に沖島周辺でよく獲れています。
“ホンモロコ”は、コイ科の琵琶湖固有種で、成魚の大きさは10cm程度になります。春から秋頃までは比較的浅い水域で生活し、4月〜6月頃にヤナギやヨシの根、水草などに産卵します。水温が下がる冬には、沖合いの深層で生活します。
春の“ホンモロコ漁”は、主に沿岸域の刺し網で行われます。そのため、サイズが大きく、産卵のため沿岸に来ることから子持ちのものが多く獲れます。 |
“ホンモロコ”は淡白な味で肉質も良く、骨が柔らかいので、佃煮や天ぷら、南蛮漬けなど、さまざまな調理方法で味わえます。また冬に獲れるものは、春の産卵のため卵を抱えており、程よく脂ものっているため、炭火で“素焼き”が絶品です。天然のホンモロコは深層で大きくなるため、白っぽく、焼くと黄金色になるのが特徴です。
今年の春は、漁獲量も増えていることなどから値段も手頃になっています。ぜひ、この機会に“琵琶湖産天然ホンモロコ”をご賞味ください。
《参考文献》
「琵琶湖の幸 読本」平成19年9月発行 滋賀県漁業協同組合連合会 |
|
 漁師が造った“鮒寿し”販売事業開始! 漁師が造った“鮒寿し”販売事業開始! |
 沖島漁業協同組合では、かねてより計画しておりました“鮒寿し”の販売事業を本格的に開始することとなりました。 沖島漁業協同組合では、かねてより計画しておりました“鮒寿し”の販売事業を本格的に開始することとなりました。
沖島漁協の“未来への取組み”の一つである「島で獲れた魚を島で加工・販売する」ということから、沖島で獲れた天然“ニゴロブナ”を塩切りから漬け込みまでの全工程を島内で行い、“漁師が造った鮒寿し”として販売致します。
春は、鮒寿しの材料となる“塩切り鮒”の仕込み作業の最盛期です。水揚げされたばかりの子持ちのニゴロブナを傷つけないように丁寧にウロコと内臓を取り、塩漬けにしていきます。手間がかかりますが、とても重要な工程です。そして、夏頃に漬け込み、発酵・熟成を経て、冬頃には食べ頃を迎えます。
 この“漁師が造った鮒寿し”が沖島の名産品として親しまれ、島の活性化につながっていくよう取り組んでまいります。 この“漁師が造った鮒寿し”が沖島の名産品として親しまれ、島の活性化につながっていくよう取り組んでまいります。
また、この事業の一環として、ご家庭で手軽に「鮒寿し作り」を楽しんでいただけるよう“塩切り鮒の予約販売”も行っております。ぜひ、ご利用ください。
《鮒寿しの御注文方法》 お電話またはFAXにて承ります。
TEL 0748(33)9511・9512
FAX 0748(33)9513 |
 沖島の新名所♪ 沖島の新名所♪ |
 ご存知ですか? ご存知ですか?
一本の木から三色の花を咲かせる桃の木を…
島民の方が植えたもので、満開の桜と競うように見事な花を咲かせています。
 今年の春、島民の間で、ちょっとした話題となっています。 今年の春、島民の間で、ちょっとした話題となっています。
新たな沖島の名所となるかもしれません♪
(撮影日:H24.4.19)) |
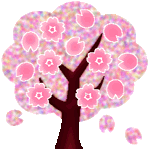 桜風景 桜風景 |
今年(H24)の桜は、冬が長かったせいか昨年より遅く開花し始め、4月中旬頃に見頃を迎えました。
沖島では島内の至るところで桜を楽しむことができます。(撮影日:H24.4.13)
|

“漁協会館付近” |

“沖島小学校” |

“公民館前” |
|
〜〜春の風物詩〜〜〜〜〜
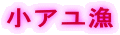
 |
小アユ漁は、“細目小糸漁”とよばれる刺し網漁で4月ごろから盛んになります。沖島では、刺し網にかかった魚を独特の方法ではずします。漁船に高く組まれた足場に網を掛け、その網を振るって魚をはずすのです。他で見られることもありますが、この方法は沖島発祥の方法です。そのため、この漁が始まる頃になると、漁船に高い足場が組まれはじめ、まさに沖島の春到来を告げる風景といえます
また6月の決められた期間ですが、今はあまり行われない“沖すくい網漁”も行われます。沖すくい網漁とは漁船の舳先にとりつけた大きな網で、アユの群れごと、すくい取る漁法です。熟練を要する漁法です。 |
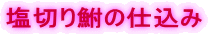
“塩切り鮒”とは「ふなずし」の材料となるもので、春に獲った琵琶湖産の天然“ニゴロブナ”を丁寧にウロコと内臓を取り、3ヵ月程度塩漬けにしたものです。このころの鮒は卵を抱えており、「ふなずし」の中でも特に美味とされています。
毎年、春が来ると、“塩切り鮒”の仕込み作業が始まります。水揚げされたばかりのニゴロブナを傷つけないように仕込むのは、とても手間のかかる作業ですが、美味しい「ふなずし」を作るには、手の抜けない重要な工程のひとつです。
|
 |
沖島の桜の開花は、少し遅めで毎年4月に入ってから咲き始めます。(写真はH22.4.6撮影)
島にはあちらこちらで桜が楽しめますが・・・特に西福寺を抜けて島の西側の桜並木は見事です。またケンケン山の登山道にある“お花見広場”では、お花見をしながら比良山系・比叡山を望む景色が楽しめます。 |
 |
 |

「秋祭り」と同様、昔から島民が集う行事のひとつです。今年は5月2、3日に行われます。お天気が良ければ、御神輿が船に乗せられ、休暇村までを往復します。 |
 |
〜〜春の味覚〜〜〜〜〜
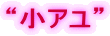
琵琶湖のアユは、春に琵琶湖から川をのぼって大きくなるアユと、琵琶湖で生活して大きくならないアユがいます。大半はこの大きくならないアユで、小アユと呼ばれ、春に漁の最盛期を迎えます。
小アユは、佃煮として食されるのが一般的ですが、島では、天ぷら、唐揚げ、南蛮漬けなどにしても頂きます。小ぶりなので骨が柔らかいのは元より、アユ独特の風味もしっかり味わえる逸品です。
※小アユの佃煮(若煮)は漁協会館前の「湖島婦貴の会」屋台または通販でお買い求めいただけます。
 |
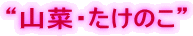
沖島では、“山菜”は4月から、“たけのこ”は5月頃から出始めます。
「煮物」にして頂くのが一般的で、山菜に小芋・ニシン(または油揚げ、棒だら)・たけのこ・ふき・赤こんにゃくなど5品くらいを一緒に炊いて頂きます。
 |
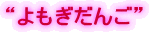
沖島に自生している“よもぎ”を摘んで作ります。中は餡子の丸いおだんごです。また、“さとだんご”と言われるもち粉によもぎと黒砂糖を入れて練ったおだんごも春の沖島の味です。 |
《参考文献》
・ 「琵琶湖の幸 読本」 平成19年9月発行 滋賀県漁業協同組合

















