 |
 H26年 H26年 |
H26年
厳しい冬が過ぎ、小アユ漁やフナ漁が始まると、“沖島の春”到来です。
沖島の春は、島の所どころに桜が咲き、山では“蕨”“筍”“よもぎ”などの山菜も採れたり・・・とのんびりとした懐かしい春の風景に出逢えます。
今年も沖島に暖かな春がやって来ました。昨年、満開とならなかった沖島の桜も今年は“昨年の分も・・・♪”と言わんばかりに満開となりました。桜満開の最中、開催した“沖島 桜まつり”にも大勢の方にお越しいただき、ご好評をいただきました。
また、春の漁も始まり、ホンモロコ、スゴモロコは少なめですが、ニゴロブナ、イサザ、スジエビは豊漁です。
春満開♪ “ニゴロブナ漁”豊漁
暖かな日が多くなり、春の漁で島も活気づいてきました。
今年もスジエビ、イサザ漁は順調で、小アユ漁も豊漁が期待されています。なかでも、“ニゴロブナ漁”は特に豊漁で、3月に入っていきなり水揚げが増加してきました。これは水温に深く関係していると思われます。また、この時期に獲れるものは子持ちで鮒ずしにすると特に美味といわれ、そのうえ、今年は形も良い物が多いので、今から鮒ずしの漬け込みが楽しみです。
“小アユ漁”は4月に入って“沖島の春の風物詩”とも言われる沖島発祥の漁も始まり、高い足場を組んだ漁船があちらこちらに見られるようになりました。今年の小アユは追加放流等で稚魚の量が多いこともあり、餌の取り合いとなるせいか…少し成長が遅れているようです。そのため、刺し網の目をすり抜けてしまうものが多く、今のところ水揚げは多いとは言えませんが、成長が進むにつれ水揚げも増加していくのでは…と期待されます。
《足場を組んだ漁船と桜》
※ 沖島漁協では今年の夏も“ふなずし手作り講習会”を開催
する予定です。お気軽にお問合せ下さいませ。
※ “沖島の鮒ずし”“えび豆”は、通信販売でお買求めいた
だけます。詳しくはこちら・・・
桜満開♪ 沖島“桜まつり”盛況
今年も昨年に引き続き、漁協婦人部“湖島婦貴の会”主催の“沖島 桜まつり〜桜色の島で郷土料理のおもてなし♪”(4月5日(土)〜13日(日)を開催いたしました。
沖島では、春になると島のあちらこちらで桜が満開となり、“桜色の島”となります。特に島の西側は見事で“桜のトンネル”と言われ、ちょっとした名所となっています。
昨年は、天候の影響か…桜に異変がおき、満開ではない中での開催となってしまいましたが、今年は“昨年の分も…♪”と言わんばかりの満開の中、開催することが出来ました。
また、今年は昨年の経験を生かしお祭りの期間を長くしたり、後半の週末にお天気に恵まれたりしたことで、多くの方にお越しいただきました。島内では、桜とともに沖島の郷土料理も楽しんでいただき、たくさんの方にご好評をいただきました。これらを励みに来年へとつなげて行きたいと思っております。
※ 今年(H26)の桜の様子は「イベント情報−桜アルバム」から
ご覧いただけます。
“花弁当”
ビワマスちらしずし・湖魚若煮・桜もち
“沖島産の天ぷら”
沖島の春スイーツ“桜もち”
春満喫♪ 5月3日“春まつり”
沖島では毎年5月に“春まつり”が行われます。昔から島民が集う行事のひとつで春まつりの頃になると、島から離れて暮らす家族がみな集まり、お正月さながらの賑わいになります。
お祭りは、前日の夜の“宵宮うつし”から始まり、島の神様“瀛津島神社”の本殿にお祭りするため、神輿倉からお神輿と太鼓を持って上がります。次の日の祭り当日、14時頃からお神輿を担いでお宮さんから下がり、町内をねり歩き、神輿倉へと向かいます。昔は、天気が良いとお神輿を船に乗せ休暇村まで往復しましたが、最近は安全に配慮して行われなくなりました。
こうして、16時頃には神輿倉に収め、公園では“なおらい”が始まります。
昔から春のお祭りになると“ゆぐみだんご”を作ったり、沖島で採れた山菜、筍を使って“煮しめ”を作ったりして家族みんなでいただきます。“ゆぐみだんご”とは、餡の入ったよもぎだんごのことで、沖島の昔ながらの呼び名です。
また、最近は祭りの次の日に子ども会の呼びかけで、“ケンケン山”へ登り、昼食会をする催しも始まりました。
このように、昔とは少しずつ様変わりしながらも、沖島の大事な行事のひとつとして受け継いで行きたいと思います。
〜〜春の風物詩〜〜〜〜〜
小アユ漁は、“細目小糸漁”とよばれる刺し網漁で4月ごろから盛んになります。沖島では、刺し網にかかった魚を独特の方法ではずします。漁船に高く組まれた足場に網を掛け、その網を振るって魚をはずすのです。他で見られることもありますが、この方法は沖島発祥の方法です。そのため、この漁が始まる頃になると、漁船に高い足場が組まれはじめ、まさに沖島の春到来を告げる風景といえます
また6月の決められた期間ですが、今はあまり行われない“沖すくい網漁”も行われます。沖すくい網漁とは漁船の舳先にとりつけた大きな網で、アユの群れごと、すくい取る漁法です。熟練を要する漁法です。
沖島の桜の開花は、少し遅めで毎年4月に入ってから咲き始めます。(写真はH22.4.6撮影)
島では、あちらこちらで桜が楽しめますが・・・特に西福寺を抜けて島の西側の桜並木は見事です。またケンケン山の登山道にある“お花見広場”では、お花見をしながら比良山系・比叡山を望む景色が楽しめます。
「秋祭り」と同様、昔から島民が集う行事のひとつです。今年は5月2、3日に行われます。お天気が良ければ、御神輿が船に乗せられ、休暇村までを往復します。
〜〜春の味覚〜〜〜〜〜
琵琶湖のアユは、春に琵琶湖から川をのぼって大きくなるアユと、琵琶湖で生活して大きくならないアユがいます。大半はこの大きくならないアユで、小アユと呼ばれ、春に漁の最盛期を迎えます。
小アユは、佃煮として食されるのが一般的ですが、島では、天ぷら、唐揚げ、南蛮漬けなどにしても頂きます。小ぶりなので骨が柔らかいのは元より、アユ独特の風味もしっかり味わえる逸品です。
※小アユの佃煮(若煮)は漁協会館前の「湖島婦貴の会」屋台または通販でお買い求めいただけます。
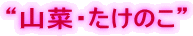
沖島では、“山菜”は4月から、“たけのこ”は5月頃から出始めます。
「煮物」にして頂くのが一般的で、山菜に小芋・ニシン(または油揚げ、棒だら)・たけのこ・ふき・赤こんにゃくなど5品くらいを一緒に炊いて頂きます。
沖島に自生している“よもぎ”を摘んで作ります。中は餡子の丸いおだんごです。また、“さとだんご”と言われるもち粉によもぎと黒砂糖を入れて練ったおだんごも春の沖島の味です。
《参考文献》
・ 「琵琶湖の幸 読本」 平成19年9月発行 滋賀県漁業協同組合